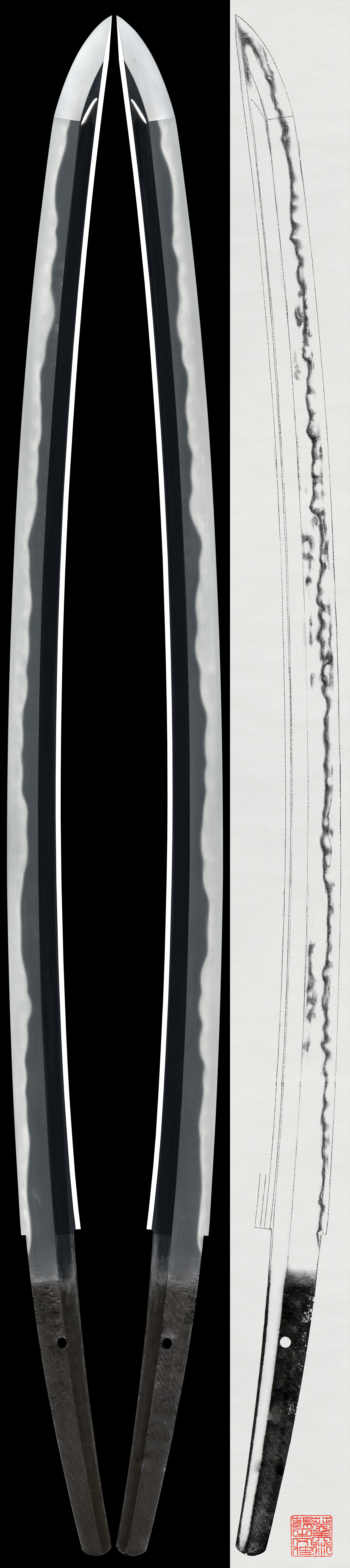前回の回答は、
月山雲龍子源貞一造
元治二年三月日
でした。
特徴: 本作はガッシリとした作品で相手を突くために製作した作品で実用的な刀です。地鉄はよく寝れて精良な地鉄となり刃紋は互の目乱れに足がよく働く作品で帽子の長く貞一のよくできた作品であると思います。
月山貞一は摂津の刀匠。本名月山弥五郎。天保七年(1836)二月、江州須越村に生まれ、七歳にて月山貞吉の養子になる。十一歳頃から修行を始め、二十歳頃には綾杉肌を習得していたと言われる。明治九年の廃刀令後も作刀ひとすじに進み、明治二十六年にはシカゴ万国博に刀を出品して受賞し、翌年明治天皇より作品お買い上げとなる。明治三十九年(1906)四月に帝室技芸員に任ぜられる。彫刻の名手としても有名。大正七年(1918)七月十一日八十四歳で没した。作刀は嘉永三年(1850)の十五歳から大正七年(1918)の没年までみられる。
地鉄は小板目が良く詰み、無地風になって地沸が付いたものが多く、映りのあるものや柾目肌、綾杉肌などがある。彫物は最も得意とするところで梵字、剣、護摩箸、旗鉾、草の倶利伽羅など簡素なものから不動明王、梅龍、倶利伽羅龍、龍虎などの密彫にいたるまで画題も豊富である。貞勝の父としても知られる。
一般に小さくなればなるほど作製は難しくなると言われるが、小振りな中にもその技量の高さが伺える。
本作は地鉄の素晴らしさとは蓮代に草の倶利伽羅竜を彫り裏には胡麻箸と爪」を見事に彫る
是非お勧めしたい作品です。
拵えは短調な拵えですが渋さのある作品です。 今後値上がりが楽しみな作品です。
=========================================
第828回:今回の鑑定 誰でしょうか?(令和7年1月4日)
刃長:70.6センチ
反り:2.1センチ
目釘穴:1個
元幅:3.40センチ
先幅:2.57センチ
重ね:0.85センチ
刀身重量:900グラム
体配:身幅広く、重ねの厚い体配の良い刀。表裏に棒樋を彫る。
地鉄:小板目肌よく錬れて地沸がつく。
刃紋:沸出来、匂口の深い互の目乱れ、帽子小丸もに返る。
ヒント ※画像をクリックすると拡大します。
=========================================
回答は次回の鑑定会コーナーで発表致します。
=========================================
(弊社都合により鑑定コーナーに関するメールには返信できませんのでご了承ください。)