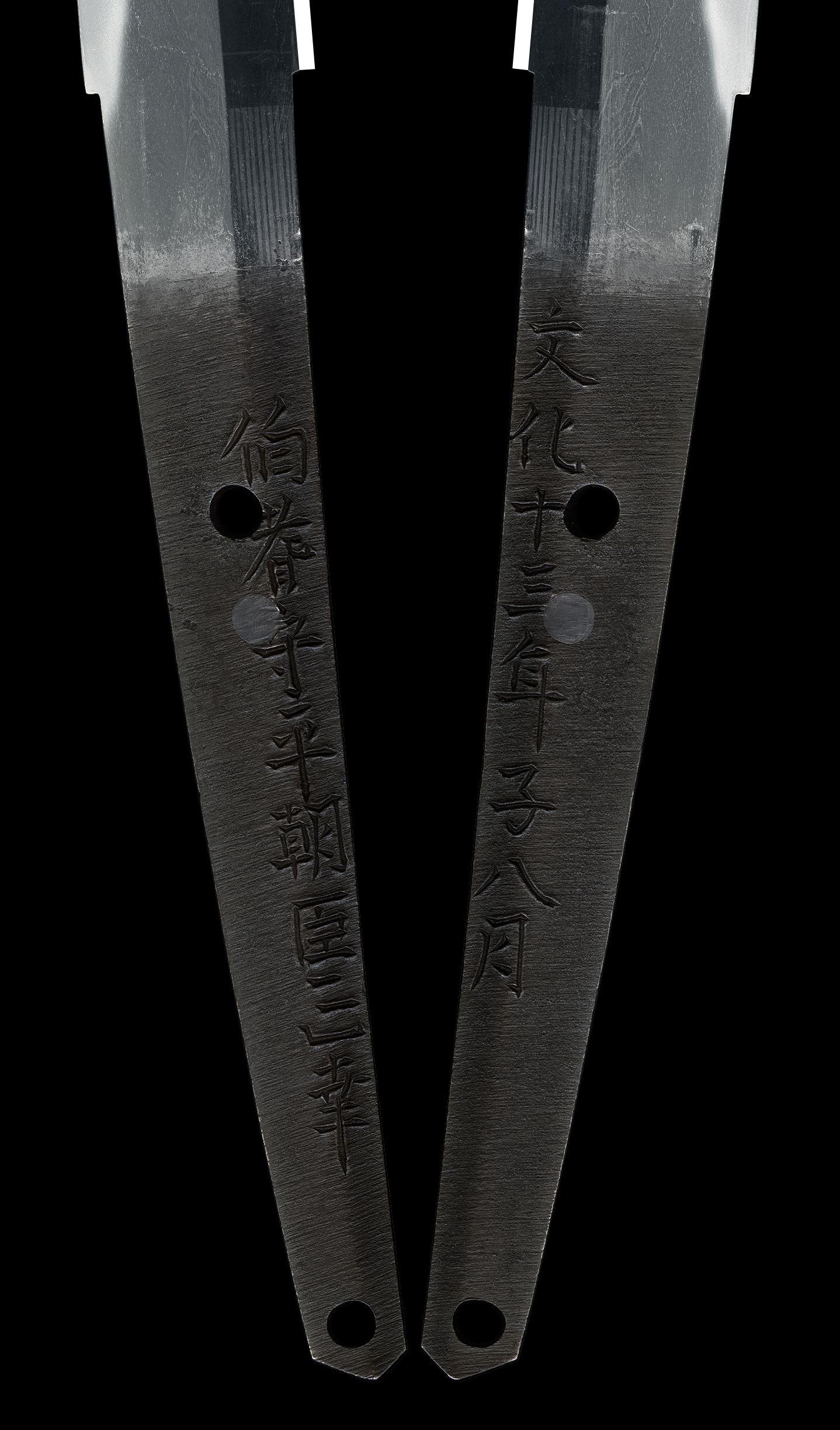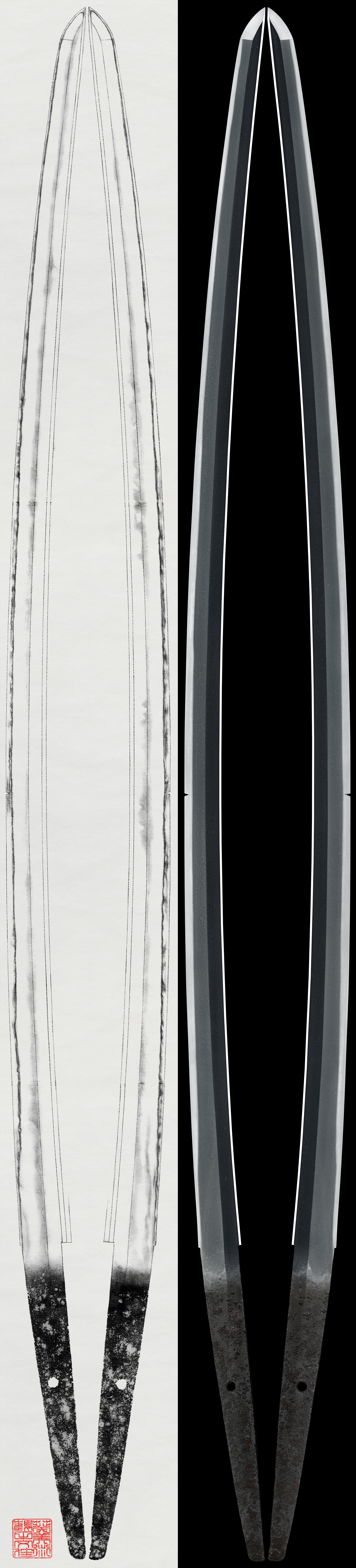前回の回答は、
伯耆守平朝臣正幸
文化十三年子八月
でした。
特徴:正近の門人で姓は伊地知初名は正良(3代目)頃からの作品があり寛政元年伯耆守を受領とともに正幸と改める。作品は文化14年におよび文政2年87歳で亡くなる。刀工教育家でもあったと言われている。元平ともよく似た作品を製作する。元平と同様茎の筋が茎尻に真ん中より少しずれた部分に筋が移動しているのは偽銘を防ぐ意味があったと言われている。これは薩摩の多くの刀工が行っておりますので注意をして見てください。
=========================================
第823回:今回の鑑定 誰でしょうか?(令和6年11月30日)
刃長:75.6センチ
反り:1.9センチ
目釘穴:1個
元幅:2.65センチ
先幅:1.35センチ
重ね:0.54センチ
刀剣重量:520グラム
体配:身幅、重ね尋常で先に行きうつ伏せ心になる。
さらに貴重なのは生茎となる点であり、棒樋等がないため鎬地がはっきりと見える。
当時の地鉄の様子が明確に見えることは実に貴重であると考えます。
さらに刃の40cmくらいの部分に大きな刃こぼれがあり戦った痕跡が見て取れます。
地鉄:鎬地は地と同様であり、無垢の地鉄とわかります。 板目肌に杢目肌、地景が入りはっきりと地鉄の様子を見て取れます。
刃紋:直刃調に刃中、小足が入り、細かな金筋が働く。帽子丸く返る。
ヒント ※画像をクリックすると拡大します。
=========================================
回答は次回の鑑定会コーナーで発表致します。
=========================================
(弊社都合により鑑定コーナーに関するメールには返信できませんのでご了承ください。)